日本国内の会社に勤めていた会社員が、海外赴任や移住などで海外勤務する場合、日本での税金はどうなるか気になる方も多いのではないでしょうか。
また、海外にいる場合の確定申告の手続きを、どのように進めれば良いかわからないという方もいるでしょう。
そこで本記事では、海外にいる場合の確定申告について詳しく解説します。
確定申告が必要になる条件や手続きの方法など詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
海外にいても日本で確定申告は必要?

結論から申し上げると、長期の海外赴任であっても、日本で所得税が発生して確定申告が必要になるケースが2つあります。
ここでは、海外にいても日本の確定申告が必要になるケースについて、それぞれ詳しく解説します。
所得税法上の居住者に該当する場合
海外に勤務・移住していたとしても、日本の所得税法上における居住者に該当する場合は、日本の所得税が発生します。
居住者の定義に関しては後ほど詳しく解説しますが、家族が日本に在住していたり、日本に住民票を残したままの場合は居住者として扱われる可能性が高いです。
居住者は日本国内外のすべての所得が課税対象となるため、海外で得た給与や投資収益も日本で申告しなければなりません。
非居住者でも国内源泉所得がある場合
海外赴任が長期に渡ったり、生活の本拠地を海外に移したりしている場合、日本の所得税法上の非居住者に当たります。
非居住者は原則として、国外で得た所得は課税されません。
しかし、国内で発生した源泉所得が一定以上ある場合、課税対象となり確定申告が必要になります。
例えば、日本の不動産からの賃料収入や日本株の配当金などが国内源泉所得に当たります。
ただし、日本の企業から受け取る給与や報酬も国内源泉所得に当たりますが、源泉徴収されていて追加の申告がない場合は、確定申告が必要ありません。
税法上における居住者と非居住者の違い
日本の所得税法では、課税対象を決める上で、その人が「居住者」か「非居住者」かを判定します。
この区分は、どこに住んでいるかではなく、「日本に生活の拠点があるかどうか」が重要です。
居住者と非居住者の定義や課税対象の範囲は、以下の表をご覧ください。
| 居住者 | 非居住者 | |
| 定義 | ・日本国内に住所を有する者 ・現在まで引き続き1年以上日本に居所を有する者 |
居住者に該当しない者 |
|---|---|---|
| 課税対象の範囲 | 国内所得・国外所得に課税 | 国内所得のみ課税 |
自身がどちらの区分に該当するか不安な場合は、日本の税務署や税理士に確認することをおすすめします。
もしも誤った判断で納税義務を怠ってしまった場合は、延滞税や追加納税などのペナルティが課される可能性があるため、十分注意しましょう。
非居住者でも確定申告が必要になる具体的な例

ここでは、非居住者の場合でも確定申告が必要になる、最も一般的に考えられる例を3つご紹介します。
日本にいたときに所有していた不動産を売却した場合
非居住者となった後でも、以前日本に住んでいた際に所有していた不動産を売却した場合、その譲渡所得は「国内源泉所得」に該当し、日本での確定申告が必要です。
不動産の売却益には「分離課税」が適用され、所有期間が5年以下なら短期譲渡、5年超なら長期譲渡として税率も異なります。
売却益の計算には、購入時の取得費や譲渡費用を差し引く必要があります。
源泉徴収だけで完結しない場合や損益通算、税還付を受けたい場合は、必ず確定申告を行いましょう。
日本に所有している住宅を貸している場合
非居住者であっても、日本に所有している住宅やアパートを第三者に賃貸している場合、その家賃収入は「国内源泉所得」に該当し、日本での課税対象となります。
賃料から必要経費(固定資産税や修繕費など)を差し引いた「不動産所得」として、原則として確定申告が必要です。
不動産管理会社が源泉徴収を行っている場合でも、控除を適用したい、赤字を繰越したい、還付を受けたいなどの理由がある場合は、申告が必須です。
適正な申告により、納税額を抑えたり、税金の還付を受けることができます。
日本企業から役員報酬や顧問料を受け取っている場合
元の勤務先や関係企業から役員報酬や顧問料を継続的に受け取っている場合は、それが日本国内での業務に基づく報酬と判断されれば、国内源泉所得とみなされます。
そのため、これらの所得は日本で確定申告しなければなりません。
振込先が海外口座であっても、源泉地が日本である限り課税されるため、確定申告が必要です。
報酬に対して源泉徴収がされていたとしても、控除や所得調整のために自主申告が必要なケースがありますので注意が必要です。
非居住者が確定申告するには納税管理人が必要

非居住者が日本で確定申告をする場合、出国前に納税管理人を選定しておく必要があります。
納税管理人とは、非居住者に代わって日本国内での税務手続きを代理する人のことです。
非居住者は日本国内に住所がないため、税務署と直接連絡を取ることが困難になります。
そうなれば申告漏れや納付遅延に繋がり、延滞税や無申告加算税が発生するリスクが高まります。
ここでは、納税管理人に関する様々な情報を解説します。
納税管理人に委託できること
納税管理人に委託できる主な業務は、日本の税務手続きに関する一連の代理対応です。
具体的には、確定申告書の提出、納税や還付の手続き、税務署からの通知や問い合わせへの対応、源泉徴収の確認などがあります。
非居住者本人が日本に不在なので、税務署との連絡窓口として機能し、税務手続きが滞りなく進むように代理対応することが役割です。
納税管理人の選定方法
納税管理人には、原則として日本国内に住所を有する個人または法人を指定します。
それ以外に必要な条件や資格はないので、親族、知人、勤務先、税理士、不動産管理会社などに依頼することが一般的です。
ただし、親族や知人に納税管理人を依頼することはあまりおすすめできません。
納税手続きが大きな負担になることや、手続きにミスが発生した際に非居住者本人にペナルティが発生することを考えると、税務のプロである税理士に依頼することが推奨されます。
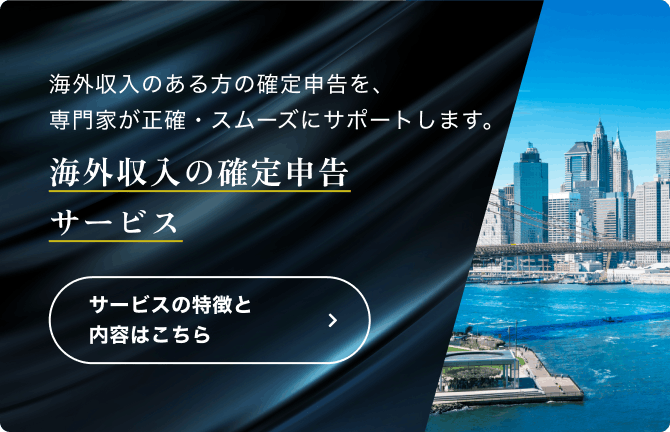
納税管理人の届出
納税管理人を選定したら、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
この届出を行うことによって、正式に納税管理人として認められることになります。
納税管理人の届出を行った後、納税管理人は税務署との連絡窓口となり、申告書の提出、納税、還付受取などを代理で行うことができます。
納税管理人に関する注意点
納税管理人を選定したり業務を依頼したりする際は、以下の点に注意しておかなければなりません。
- 原則税務判断や申告内容の作成はできない
- 責任は非居住者本人にある
- 納税管理人が辞任することもある
原則税務判断や申告内容の作成はできない
納税管理人はあくまで事務的な代理人であり、税務の専門家ではない限り、申告書の作成や税務判断を行う権限はありません。
複雑な控除計算や損益通算などを正確に行いたい場合は、税理士に別途依頼が必要です。
責任は非居住者本人にある
納税管理人は、非居住者に代わって申告や納税を行うことはできますが、納税義務自体は非居住者本人にあります。
申告漏れや納付遅延があれば、延滞税や加算税などのペナルティは本人に課されます。
納税管理人が辞任することもある
納税管理人は本人の了承なく辞任することも可能です。
そのため、事前に責任範囲や連絡体制を明確にし、信頼関係を築いておくことが不可欠です。
長期間海外にいる場合、定期的な確認や報告の体制を整えておきましょう。
非居住者がe-Taxで確定申告することは可能?

通常の確定申告は、e-Taxを活用することでオンライン上で実施することが可能です。
海外にいる場合でもe-Taxを活用することができれば、納税管理人を選定しなくても確定申告ができるのではないかと考えているかもしれません。
しかし、結論から申し上げると、海外にいる非居住者は、原則としてe-Taxを利用して日本の確定申告を行うことはできません。
e-Taxを利用するには、マイナンバーカードが必要で、マイナンバーカードに紐づけられている署名用電子証明書機能によって本人確認をしています。
しかし、国外に転居した場合はマイナンバーカードの効力が失われ、署名用電子証明書機能も無効になります。
非居住者はe-Taxを利用することができないため、必ず出国前には納税管理人を選定して届出を提出しましょう。
海外にいる場合も確定申告は忘れずに
海外にいる場合でも、日本の所得税法上で居住者とされるケースや、非居住者であっても国内に所得がある場合は、確定申告が必要になります。
特に非居住者はe-Taxが利用できないため、確実な申告のためには納税管理人の選定が不可欠です。
申告内容や手続きが複雑になることも多いため、納税管理人には税務の専門家である税理士を選ぶことを強くおすすめします。
納税管理人を依頼する税理士をお探しの方は、MACコンサルティンググループへお気軽にご相談ください。
日本や海外の税務に精通した税理士が、税務関係業務を丁寧にサポートします。
