海外に資産を持つと、日本とは異なる『プロベート』という制度が待ち受けています。
これを知らないと、資産が凍結されて家族が困ることもあります。
プロベートは、日本にはない海外特有の相続制度で、これを理解しておかなければ望ましい形で資産を相続することができなくなってしまうリスクがあるため、注意が必要です。
本記事では、プロベートとはどのような制度か、対象となる国や資産、手続きの流れ、回避策などを詳しく解説します。
これから海外資産を所有する予定のある方や、すでに海外資産を所有している方などは、ぜひこの記事を参考にしてプロベートについて理解を深めてください。
目次
プロベートとは?

プロベートとは、主に英米法系の国で採用されている、被相続人の遺言書の有効性を確認し、遺産を法的に管理・分配する裁判手続きです。
遺言執行者や遺産管理人が裁判所の監督下で、遺産の目録作成、債務の弁済、税金の支払いを行い、最終的に相続人へ遺産を分配します。
この手続きを経なければ、資産の所有権移転が認められません。
プロベートの主な目的は、被相続人の遺産を法的にかつ公正に管理・分配することです。
プロベートによって遺産をめぐるトラブルを防ぎ、資産の所有権が法的に正当な形で次世代に引き継がれることが保証されます。
日本と海外の相続制度の違い
プロベートがある外国と、プロベートがない日本とでは相続制度に大きな違いがあります。
日本の相続制度は「包括承継主義」と呼ばれます。
これは、被相続人が亡くなった瞬間に、不動産や預金といったプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの負債も全てが法的に相続人へ一体として引き継がれる考え方です。
その後、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって、誰がどの資産を相続するかを具体的に決定し、手続きは基本的に当事者間で私的に進められます。
一方、プロベートは「清算主義」という考え方に基づいた制度です。
遺産はまず、個人から切り離された1つの財産(遺産財団)として扱われ、裁判所の監督下に置かれます。
裁判所が任命した遺産管理人などが、まず被相続人の債務を全て弁済し、税金を支払います。
この「清算」手続きを経て、最終的に残った純資産だけが、遺言や法律に従って相続人に分配される仕組みです。
資産所有者が日本人でもプロベートの対象になる
資産の所有者が日本人であっても、プロベート制度のある国に資産を所有している場合、その資産の相続はプロベートの対象となります。
これは、国際相続において「相続準拠法」というルールが関係するためです。
多くの国では、不動産などの資産はその所在地の法律に基づいて相続手続きが行われると定められています。
つまり、被相続人や相続人が日本人であっても、例えばアメリカに不動産を持っていれば、その不動産の相続手続きはアメリカのプロベートに従って進められることになります。
日本の民法ではなく、資産がある国の法律が優先されるため、日本で馴染みのないプロベートという手続きが必要になるのです。
プロベートの対象資産と制度がある国・地域

ここでは、プロベートの対象となる資産や、プロベート制度がある国や地域を紹介します。
プロベートの対象資産
プロベートの対象となるのは、被相続人が単独名義で所有していた資産です。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 不動産:被相続人の単独名義になっている土地や建物など
- 銀行口座:被相続人名義の預金口座、貯金口座など
- 投資資産:被相続人名義の株式、債券、投資信託など
- 動産:自動車、美術品、骨董品、家具など
一方で、以下のような資産は、所有権が自動的に移転する仕組みがあるため、通常はプロベートの対象となりません。
- 信託内の資産:受託者を通じて自動的に受益者へ引き継がれる
- 受益者が指定されている資産:生命保険や確定拠出型年金、退職金など
- ジョイント資産:夫婦などによる共同名義の銀行口座や不動産など
自身の所有する資産がプロベートの対象となるかどうかわからない場合は、国際相続に詳しい税理士や弁護士に相談しましょう。
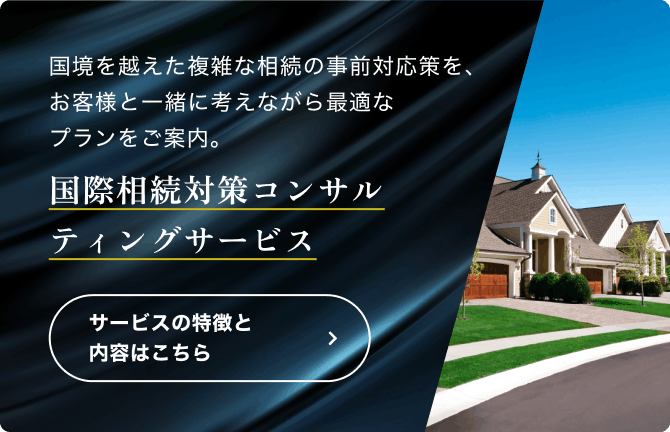
プロベート制度がある主な国や地域
プロベート制度は、主に英米法(コモン・ロー)を採用している国や地域に存在します。
代表的な国や地域は、以下の通りです。
- アメリカ
- イギリス
- カナダ
- オーストラリア
- ニュージーランド
- 香港
- シンガポール
- マレーシア
これらの国や地域は、かつてイギリスの植民地であった歴史を持つことが多く、共通の法制度を基盤としています。
上記の国や地域に資産を所有している、または所有しようとしている方は、プロベート制度をよく理解しておきましょう。
プロベートの手続きの流れ

プロベートの手続きは、国や地域によって細かな違いがありますが、ここでは一般的な流れを解説します。
- 申立て
- 遺言執行者の任命と通知
- 遺産調査と目録作成
- 債権者への通知と債務の支払い
- 遺産の分配と手続き完了
1.申立て
被相続人が亡くなった後、遺言書で指定された遺言執行者、または遺言がない場合は相続人の代表者が、被相続人の最後の居住地を管轄する裁判所にプロベートの申立てを行います。
この際、死亡診断書と遺言書(あれば)を提出し、裁判所は遺言書が法的に有効であるかどうかの審理を開始します。
この申立てがプロベート手続きの公式なスタートです。
2.遺言執行者の任命と通知
裁判所は、提出された遺言書が有効であると判断した場合、遺言書で指名されている遺言執行者を正式に任命し、「遺言執行者証明書」を発行します。
遺言がない場合は、相続人の中から「遺産管理人」を任命し、「遺産管理人証明書」を発行するのが一般的です。
この証明書を持つことで、執行者・管理人は被相続人の資産にアクセスし、法的に管理する権限を得ます。
その後、執行者は全ての相続人や利害関係者に対して、プロベートが開始されたことを法的に通知する義務を負います。
3.遺産調査と目録作成
遺言執行者は、被相続人が所有していた全ての資産を特定し、その価値を正当に評価しなければなりません。
これには、不動産の鑑定評価、銀行口座の残高確認、株式や投資信託の時価評価などが含まれます。
特定した全ての資産は「遺産目録」としてリストアップし、裁判所に提出する必要があります。
この目録は、後の債務の支払いや遺産分配の基礎となる非常に重要な書類です。
資産の特定と評価には、数ヶ月かかることもあります。
4.債権者への通知と債務の支払い
次に、遺言執行者は、被相続人に対して債権(貸付金など)を持つ可能性のある全ての債権者に対して、プロベート手続きが開始されたことを公式に通知します。
これは、地域の新聞などへの公告によって行われることが一般的です。
債権者は定められた期間内(通常3〜6ヶ月)に請求を申し立てる必要があります。
執行者はその請求が正当なものかを確認した上で、遺産の中から被相続人の借金、未払いの税金、医療費などを支払わなければなりません。
全ての債務を清算しなければ、相続人への遺産分配はできません。
5.遺産の分配と手続き完了
全ての債務、税金、そしてプロベート手続きにかかった費用(弁護士費用など)を支払った後、残った純資産を遺言書の指示、または現地の相続法に従って各相続人に分配します。
分配が完了したら、執行者は全ての収支を記録した「最終会計報告書」を作成し、裁判所に提出しなければなりません。
裁判所がこの報告書を承認し、全ての手続きが適切に行われたことを確認すると、「遺産閉鎖命令」を出し、プロベート手続きは正式に完了となります。
プロベートが適用されることのデメリット
プロベートが適用されることには、日本の相続手続きにはない特有のリスクやデメリットが存在します。
主なリスクやデメリットは、以下の通りです。
- 資産の長期凍結と高額な費用
- 手続きの煩雑さと精神的負担
- プライバシーの公開
資産の長期凍結と高額な費用
プロベートは裁判所が関与する厳格な手続きのため、完了までに長い時間を要するのが最大の問題点です。
簡単なケースでも1年、不動産が絡んだり相続人間で意見の相違があったりすると2年以上かかることも珍しくありません。
その間、被相続人名義の銀行口座からの出金や不動産の売却は一切できなくなり、資産は完全に凍結されます。
これにより、日本の相続税の納税資金を遺産から捻出できない、といった問題が生じかねません。
米国で不動産を持っていた日本人のケースでは、売却できずに納税資金を自己資金で立て替えざるを得なかった事例もあります。
さらに、手続きには高額な費用が必要です。
裁判所への申立費用、遺産鑑定費用に加え、現地の弁護士への報酬が大きな負担となります。
弁護士費用は遺産総額の数パーセントと定められている場合も多く、数百万円以上の出費となる可能性があり、結果的に相続人が受け取れる遺産が大幅に目減りしてしまいます。
手続きの煩雑さと精神的負担
プロベート手続きは、現地の法律に基づいて、現地の言語で進められます。
相続人は日本の戸籍謄本や除籍謄本といった書類を取り寄せ、それらをすべて英訳し、さらに公的な認証(アポスティーユなど)を得て提出しなければなりません。
これらの書類準備だけでも、多大な時間と労力がかかります。
また、裁判所とのやり取りや遺産管理人の選任など、日本では馴染みのない法的手続きを、大切な家族を失った悲しみの中で進めなければなりません。
言葉の壁や商慣習の違いも相まって、相続人にとって計り知れないほどの精神的負担となることが多く、これが原因で相続人間の関係が悪化してしまうケースもあります。
プライバシーの公開
プロベートは公開の裁判手続きであるという点が、日本の相続との大きな違いです。
手続きの過程で裁判所に提出された遺言書、財産目録(どのような資産がいくらあるか)、そして誰が何を相続したかといった詳細な情報が、全て公の記録として誰でも閲覧できる状態になります。
これは、家族のプライベートな財務情報が、近隣住民やビジネス関係者、さらには悪意を持つ第三者にも知られてしまうリスクを意味します。
特に多くの資産を所有している場合、家族のプライバシーが侵害されるだけでなく、相続人が詐欺などのターゲットにされる危険性も高まるため、非常に大きなデメリットです。
主なプロベートの回避策

プロベートを回避する代表的な対策として、以下のものが挙げられます。
- 生前信託(Living Trust)
- 共同名義(Joint Tenancy)
- 死亡時譲渡証書(TODD:Transfer On Death Deed)
- 死亡時支払制度(POD:Payable On Death)
生前信託(Living Trust)
生前信託は、資産の所有権を自分自身(委託者)から「信託」という法的な器に移す手続きです。
「信託」は資産の所有者に代わって資産を管理し、所有者が亡くなった後は、あらかじめ指定しておいた後継受託者が、信託の指示書(信託契約書)に従って、指定された受益者(相続人)へ資産をスムーズに引き継ぎます。
資産の名義は「個人」ではなく「信託」になっているため、個人の死亡を証明するプロベート手続きが不要です。
費用はかかりますが、プライバシーを守りつつ、最も確実かつ柔軟に資産承継をコントロールできる方法として広く利用されています。
共同名義(Joint Tenancy)
共同名義、特に「生存者権付き共同名義」は、主に夫婦間で利用されるプロベート回避策です。
不動産や銀行口座をこの形式で二人以上の名義で所有すると、名義人の一人が亡くなった場合、その人の持分は自動的に生存している他の名義人に移転します。
遺言書の内容に関わらず所有権が移転するため、亡くなった方の持分はプロベートの対象外となります。
手続きが比較的簡単というメリットがありますが、名義人全員の同意がなければ資産の売却などができなくなるという点に注意が必要です。
死亡時譲渡証書(TODD:Transfer On Death Deed)
死亡時譲渡証書(TODD)は、主に不動産を対象としたプロベート回避策です。
不動産の所有者が生前に、死亡した際にその不動産の所有権を引き継ぐ受取人を指定する証書を作成し、登記しておきます。
所有者が生きている間は、不動産の所有権は変わらず、自由に売却したり、TODDを撤回したりすることも可能です。
そして所有者が亡くなると、その不動産はプロベートを経ることなく、登記簿上で自動的に指定された受取人へ名義が移転します。
ただし、全ての国や地域で利用できるわけではないため、資産所在地の法律を確認しておきましょう。
死亡時支払制度(POD:Payable On Death)
死亡時支払制度(POD)は、銀行口座や証券口座などの金融資産に適用されるプロベート回避策です。
口座の所有者が金融機関との契約で、自身が死亡した場合に口座の残高を受け取る受取人を指定しておきます。
所有者が亡くなった際、指定された受取人は死亡診断書などの必要書類を金融機関に提出するだけで、プロベート手続きを経ずに口座の資金や有価証券を受け取ることが可能です。
TODDと同様に、所有者は生前、自由に口座を利用したり、受取人を変更したりすることが可能で、手軽に設定できるため広く利用されています。
プロベートに関する注意点

プロベートに関しては、制度の仕組みを理解するだけでなく、実務上のいくつかの重要な注意点があります。
日本の相続税の申告・納税期限とのズレに注意する
日本では、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納税をしなければなりません。
しかし、プロベート手続きは完了までに1年以上かかるのが一般的です。
つまり、海外資産がプロベートによって凍結され、売却も現金化もできない状態のまま、日本の納税期限が先に来てしまうという深刻な問題が発生します。
その結果、相続人は海外資産をあてにできず、自己資金や他の国内資産で高額な相続税を立て替えなければならなくなるリスクがあります。
プロベート回避策の不備に注意する
生前信託などの対策は非常に有効ですが、「設定しただけで安心」してしまうケースが後を絶ちません。
例えば、信託を設定しても、その信託の中に資産を移転(登記変更など)する「ファンディング」という手続きを忘れてしまうと、その資産は信託の対象外となり、結局プロベートが必要になってしまいます。
また、共同名義は手軽ですが、自分の意思だけで資産を売却できなくなる、資産の共有割合によっては日本で贈与税の課税問題が生じる可能性がある、といったデメリットも理解しておく必要があります。
回避策は、その実行と維持管理までが重要です。
遺言書の有効性を確認する
日本で作成した遺言書が、海外で法的に有効と認められるとは限りません。
特に、自筆証書遺言は、プロベートのある国では証人がいないため無効と判断される可能性が高いです。
海外資産については、日本の法律だけでなく、現地の法律で定められた厳格な要件(2名以上の証人の前での署名など)を満たした遺言書を別途作成しましょう。
または、国際的に通用する形式の遺言書(秘密証書遺言など)を検討する必要があります。
遺言書が無効となれば、現地の法律に従って意図しない形で資産が分配される可能性があるため、注意が必要です。
プロベートに関するよくある質問
プロベートに関してよくある質問と回答を、以下にまとめます。
Q.プロベートの費用はどれくらいかかりますか?
費用は遺産総額や手続きの複雑さによって大きく変動しますが、一般的に日本の相続手続きよりも高額になります。
主な内訳は、現地の弁護士に支払う報酬(遺産総額の3~5%程度が目安)、裁判所への申立手数料、遺言執行者や遺産管理人への報酬、不動産鑑定費用などです。
シンプルなケースでも数十万円から、遺産総額や手続きの難易度によっては数百万円以上の費用がかかることも珍しくありません。
Q.遺言書がない場合はどうなりますか?
遺言書がない場合、「無遺言相続」として、資産所在地の法律に基づいて手続きが進められます。
裁判所が遺産管理人(Administrator)を任命し、その監督下で資産の分配が行われます。
この法定相続のルールは日本の民法とは大きく異なり、配偶者が全額を相続できるとは限りません。
例えば、配偶者と子がいる場合、それぞれ決められた割合で分配されるなど、被相続人が意図しなかった結果になるケースも十分に考えられます。
手続きも通常より複雑で、より多くの時間がかかるでしょう。
Q.海外預金が少額の場合でもプロベートは必要ですか?
必ずしも必要ではありません。
多くの国や地域では、少額遺産向けの簡易的な手続きが用意されています。
遺産総額が一定の基準額(地域によって異なる)を下回る場合、正式なプロベートを経ずに、宣誓供述書を金融機関に提出するだけで資産を受け取れることがあります。
ただし、この制度が利用できるかどうかは、資産の種類や現地の法律によるため、少額であっても専門家への確認は必要です。
Q.日本に住んでいる相続人が、海外資産の遺言執行者になれますか?
法律上、なること自体は可能ですが、実務上は多くの困難が伴うでしょう。
手続きを円滑に進めるため、裁判所はその国や地域の居住者を遺言執行者とすることを好む傾向があります。
非居住者が執行者になる場合、手続きの遅延を懸念されたり、万一の事態に備えて高額な保証金を裁判所に預けるよう求められたりすることがあります。
そのため、現地の親族や弁護士、信託会社などに遺言執行者を依頼するのが一般的です。
Q.生前信託さえ設定しておけば、全て安心ですか?
生前信託は非常に有効な手段ですが、設定しただけでは機能しません。
最も重要なのは、信託を設定した後に、不動産や銀行口座などの資産の名義を個人から信託へ移しておくことです。
この名義変更を忘れた資産は、信託の対象外となり、結局プロベートが必要になってしまいます。
また、信託を設定した後も、資産の増減に合わせて定期的に内容を見直すなど、適切な維持管理が必要です。
プロベートは専門家に相談しよう
海外資産にはプロベートという特有の相続手続きがあり、資産凍結や費用の増大など、残された家族の大きな負担となり得ます。
生前信託などの対策は有効ですが、国ごとに制度が異なり手続きは複雑です。
特にアメリカ・イギリス・オーストラリアなどに不動産や金融資産を持っている方は、早めに準備をしておくことで大きなリスクを避けられます。
大切な資産を円滑に承継するため、まずは国際相続に詳しい弁護士や税理士などの専門家へ相談することをお勧めします。
MACコンサルタンツは、国際相続や海外資産の税務に精通したスタッフが在籍しており、プロベートをはじめ、様々な国際資産に関するご相談を受け付けております。
お困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
